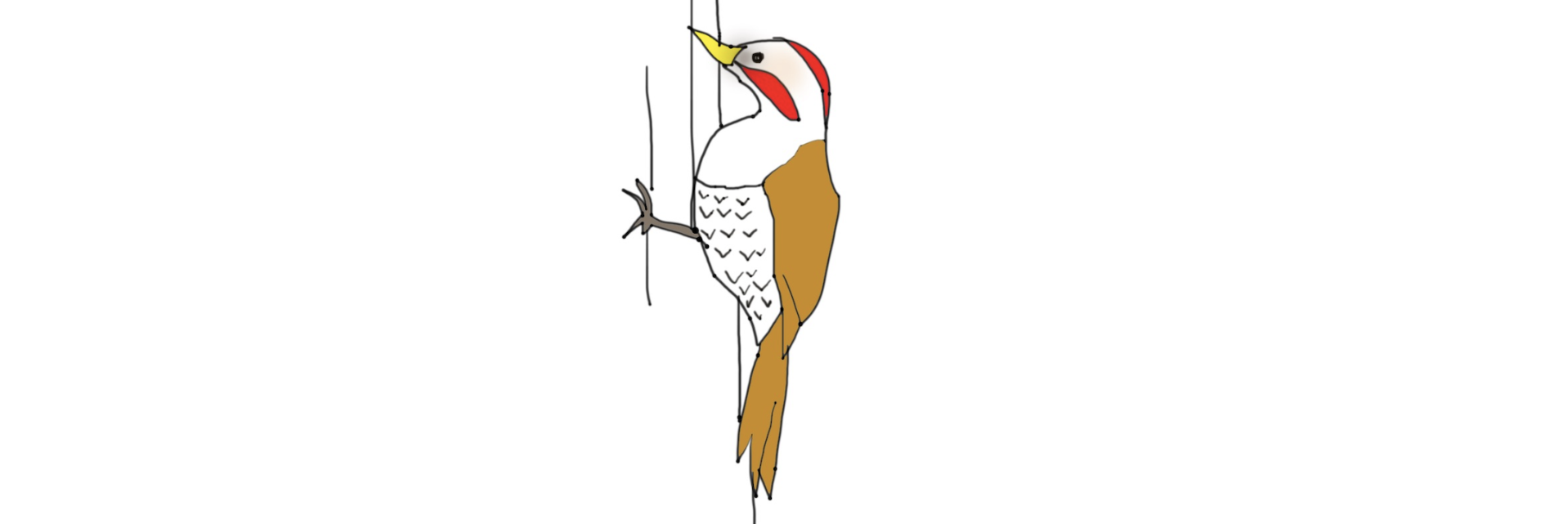AIO
SEOがgoogleなどの検索エンジン最適化して上位表示させる戦術に対して、AIOはchatGPTやgeminiなどのAIに対して参照されるよう施す戦術となります。それぞれのAIがどのようなアルゴリズムで動いているか把握する必要があるものの、現時点で筆者が有効だと考える5つの要素があります。
基準の異なる「信頼できるコンテンツ」の可能性
AIは検索エンジンのアルゴリズムと同様に、信頼できるコンテンツが好きです。AIを作る側に立ってみると、雑な情報やおかしな情報をたくさん収集して解析したとしても、それは使い物にならないAIを作ることになります。信頼できるコンテンツかどうかAIは選別しているので、AIOを考えるうえではAIの基準で信頼できるコンテンツを作っていかないといけなくなります。
なにをもって信頼できるコンテンツとするか、いままでは主にGoogleがこの基準を作ってきて、コンテンツ制作者はそれに習ってコンテンツを作ってきた側面もあるかと思います。2010年台後半のある時点から、記事が長く、ユーザーが滞在する時間が長く、ドメインが古く、著者に権威性があり、センシティブなワードやジャンルを含まないことが、良いコンテンツであると判断されてきました。
でも、それはGoogleが広告を扱っているので、より広告枠が多く表示できるようGoogleがコンテンツ制作者に求めていた、と考えることもできます。Googleにとっても、検索ユーザーにとっても、一番いい形をGoogleが模索した結果ともいえます。
では、AIOではどうか。もしかしたら今のGoogle基準がAIに好まれるかもしれないし、端的で短文で箇条書きの方がむしろ好まれるかもしれません。ChatGPTを始めPerplexityやDeepseekやClaudeなど、Google以外のサービスも「信頼できるコンテンツとはなにか」を研究にしていると思います。
パッと思いつく信頼性の高そうな情報としては査読された論文が思いつくのですが、論文には一般的で生活密着な情報はあまり出てきません。ユーザーが欲しい情報はハウトゥーや分析情報だけじゃなく、近隣でのランチ情報だったり、噂になっている有名人の情報だったり。AIが論文を読み終わったあと、検索したりしてコンテンツを収集するようになってきているので、一周まわってSEOがAIOである可能性もあります。
SEO基準の「信頼できるコンテンツ」なのか、AI基準の「信頼できるコンテンツ」なのか、その背景をよく考えて、将来どうなっていくか見極めていく必要があると思います。
botを受け入れる
サイトを運営していると、日々、大量のbotが届きます。googleのクローラーだけでなく、アクセス解析系や、謎のアタックを探るbot、サイト生存を確認するbotなどがあります。その中に生成AIが取得しているbotがあると考えられるため、日本からのアクセスのみ受け入れたり、googleのみbotを受け入れる運用をしていると機会損失となり得ます。
セキュリティや負荷、不正確なアクティブ数とのトレードオフになるかもしれませんが、生成AIからのbotの可能性を今後は考慮していく必要はあると思います。
人間が介在する価値の再定義
AIにできないことはなにか、これが今後のテーマになると思います。生成AIは膨大なデータをもとに一般的な情報をまとめることは得意ですが、個人的な体験や独自の視点は提供できません。
- ツールを実際に試して得た使用感や気づき
- この手法を試した結果の成功例や課題点
- 特定の業界や地域でのリアルな事情や背景
こういったことはAIは後追いで知ることになるので一次情報としては提供はできず、参照して提供することになります。参照されることがAIOになると筆者は考えます。
ほかにも、どのような立場に立つのか『判断』することや、最新情報もAIは苦手だと思っています。ちなみに、AIが苦手とよく言われる会話の双方向や、トレンドを横断して生成することは筆者としては苦手とはあまり思っています。かつては筆者も双方向性については苦手だろうと思っていましたが、J-Moshiを見て考えを改めました。相手が相槌を打つとAIかどうかわからなくなります。
トレンドについては、研究されたら早い段階で攻略してトレンド生成してくるだろうと踏んでいます。広告代理店が流行らせたくてもAIがそれを上回る流行りをしかけてくるかもしれません。すこしこわい気もしますけど、今までとは違う体験を生んでくれそうでわくわくしています。
最初に結論、ピラミッド型構成
AIが読みやすいものとして以下のものがあげられます。各AIに聞いてみたらこれが読みやすいと答えが返ってきたのでまとめます。
- 結論ファースト
- 比較表など表がある
- 1文は20〜30文字くらい
- 箇条書きが多い
ピラミッド型の構成で、結論が最初、その後に理由や具体例、補足情報が加わったもの。表現としては簡潔で、リストや表を使い、事実を羅列されている方が好むようですね。
人間から見たら、吹き出し表現があったり、イラストや挿絵とか、ちょっとくらい寄り道した文章のほうがおもしろかったりするのですけど、AIは超効率的。シンプルで簡潔で事実をポンポン書かれていた方がAIOとしては良さそうです。
もしかしたら将来的に、人間が読む文章とAIが読む文書が、同じページでも違うこともあるかもしれません。人間がおもしろいと思っている記事の裏側で、AIがおもしろいと思う文章を読んでいる。今でも構造化データでソース上にはあっても人間が読むものは別になっているので、AI向け構造化データが生まれる可能性もあります。
SGEを追う
SGE(Search Generative Experience)は、GoogleがGeminiを活用して検索の一番上にAI要約した文章を出す機能のことです。2023年にテスト導入して、2024年に正式導入、2025年現在ではまだ進化の過程で見た目や動作の更新が頻繁にあります。
これまでの項目はAI参照を軸に書いてきましたが、SGEを追うことはGoogleの検索画面のAI要約の場所に出すことを目的としています。SEOの一環としてやっていくイメージです。
SGEの最適化として大事なのは「引用される」ことかなと思います。AIが引用しやすいコンテンツ構成としては前述のピラミッド型の構成の他にこのあたりが考えられます。
- Q&A形式 (Aとは?Bである)
- 定義を明確に (AとはBのこと)
- ステップごとの解説
- 要点まとめ
- 内部リンクを強化 (関連情報を集約)
具体的にSGEの追い方について、現時点ではGoogleにおいても具体的な対策がかかれていません。公式情報ではSGE登場時点での機能概要に留まっています。Google自身もAIに対応しきれていない、と思うのが正直な感想です。
生成 AI による検索体験 (SGE) のご紹介 – Google Japan Blog
https://japan.googleblog.com/2023/08
Search Labs の「AI による概要など」 – Google 検索 ヘルプ
https://support.google.com/websearch/answer/13572151
当サイト「AIコツコツ」ではSGEやAIOについて調べたことを共有していくのでぜひフォローやブックマークをお願いします。AIの進化に合わせて、一緒に進化していく必要があります。読者のみなさまと一緒に学び続けていけたらと思います。